今週の儲かる繁盛店の視点 第583話:「労働集約型企業で確実に利益アップ出来る企業と出来ない企業の違い」
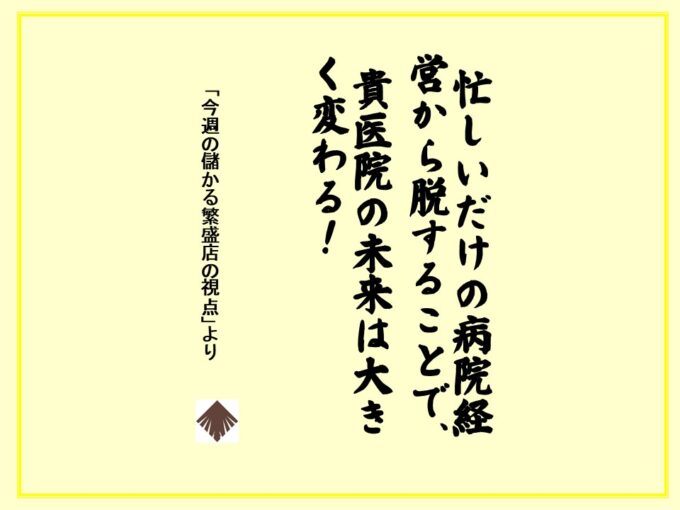
「頑張っているんですが、赤字ギリぎりなんです。とある病院の経営者からのご相談です」
聞くところによると、診療報酬点数の改定で実質収入が減り、患者さんはいるのに、人手不足で、業務が滞り厳守減益になってしまう見込み、とのこと。
厳しい状況、お気持ちお察しいたします。
前職時代、スーパーマーケット店舗統括に携わっていた時、毎日3千人超のお客さんが来てくれる店に対し、闇雲に人を削減をしたことで、減収減益を招くといった厳しい結果を出してしまった時がありました。
当時、人時生産性の改善策がよく解らず、目標を提示だけで、店長会議でも、具体的な話や指導をおこなってこなかったからです。
いい意味では、店長に自由にやってもらっていたわけですが、悪く言えば現場に丸投げしていたわけです。
そんな状態でしたから、現場が疲弊するのは無理もなく、厳しい結果が出づけた時のことを今でもハッキリ覚えています。
今であれば、現場に出向き、全ての作業項目を洗い出し、どれぐらいかかり、どこの作業が滞っているのかを特定します。
作業項目を洗い出すことで、非効率な作業も浮き彫りになります。それを一表にして、主管部門に、年間このくらいの人件費が浮いてくるので止めるか簡素化して欲しいと要請を行います。
ようは、経費の中で最も高い構成比となる人件費の中のムダな作業を、緊急処置をして早く食い止めないと、企業生命にかかわってくるからです。
「出来るとこまでやって・・・」「切りのいいとこまでやったら・・・」と言ってる時間はありません、違和感を感じたら即座に立ち止まって、原因を特定し解決していく。この流れからつくってということです。
そうは言っても、闇雲に作業を減らせばすぐに、患者さんにも伝わり、患者数減に直結します。なぜなら、病院や介護事業は、1人のお客様の何度も来ていただくことによって、それが大きな利益をもたらしてくれる地域型ビジネスモデルだからです。
なので、コストを下げながら、何度も来ていただく仕組みが一刻も早く欲しいのです。そこで病院業務を忙しくさせている非効率な業務に注目し、それを、経営プロジェクトとして解決していく道筋を作ってみるというわけです。
――――院内の非効率な業務を、調べてみることはできますか? とお聞きすると
「うーん?」と口こもられます
「病院経営は非営利が原則なんです。医師、看護師、管理栄養士、医療事務とそれぞれの役割が分かれてます。作業の内容を調べるといったことは今までやったことがありませんので、抵抗感はあると思います。
しかし、そういったことで、患者さんを待たせることに繋がってるのも事実だと思っていますのでやる必要はあると思ってました。抵抗感なくやる調べていく方法ってあるのでしょうか?」
―――今、病院にとって一番の問題はは何ですか?
「人件費増と人手不足です。それと 収入減です」
――――経営としてどこで人手不足が起きているか?それを改善するために、「調査に協力していただきたい」とお願いしてみる。ことはできますか?
「そういった目的でしたら、出来ると思います。外来患者数は曜日によって差があるので、事前予測ができれば、長時間労働が改善できるやもしれません。」
おっしゃる通り、経費で最も構成比の高い人件費が、どういう作業に使われているのかが分れば、解決の道筋もみえてくるということです。
実際にやってみるとわかるのですが、非効率業務の中には、過去に経営者が有効手段として言ってきたことが形骸化してたり、費用対効果が出ていないものが想像以上にあることに気づきます。
経緯者としては耳の痛いものもあるのも事実ですが、こういった場で明らかにすることで、失敗を恐れない社風に変わるチャンスもあるということです。
そうは言っても
業務改善と聞くと、「抵抗勢力を納得させて・・・」とか「人員整理やリストラ…?」といったことで、人間関係がギクシャクすることを連想するものです。
確かに
一昔前、売上が上がっていた時代では、各部門が経費予算をもっていたため部門間の壁がありました。しかし、今は、経費予算がないため、壁はなくなりつつあります。
むしろ現場からは、そういったことに気づいていない経営に対し、一刻も早くやってほしいという声が多いのが実情です。
そういう意味では、病院内の各部署が抱える悩みについて、早急に解決していく仕組みづくりこそが喫緊の課題と言えます。
この流れを、月に一回のペースで実施していくことで、毎年、増収増益になっていく企業や団体が増えつづけています。
さあ、貴医院ではまだ、減収減益の実態を掴めぬままの経営を続けますか?
それとも、問題を特定し、悩みを解決していく仕組みを作ることで、病院経営黒字安定化への一歩を踏み出しますか?
著:伊藤 稔
