今週の儲かる繁盛店の視点 第591話:「なぜ、総合病院経営で業務改革が重要なのか?早期実施が出来る病院と出来ない病院の違い」
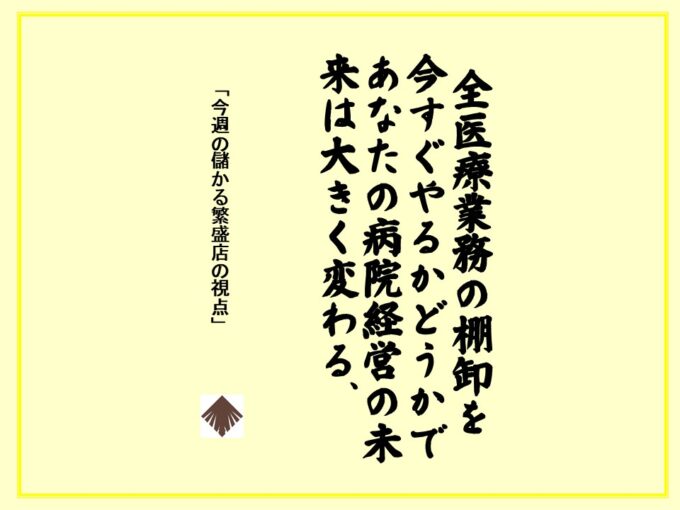
「医療事務の人員ってどのくらいが適正なのでしょうか?」総合病院経営者からのご相談です。
お話をお聞きすると、医師の長時間労働の改善を機に、医療補助業務の人員を増やしてこられたそうです。
ところが、思っていたほどトータル人件費は下がらず、賃上げで、再び人件費が増えてきているとのこと
おっしゃる通り、トータル人件費を下げるには、勤務時間を短くするか?単価を下げるかの何れかになります。
一見どちらでも同じに見えますが、効果の出方はかなり異なってきます。
勤務時間を短くするのは、高い効果が得られ比較的長く効果がつづきますが、プロジェクトを組んで全体の業務量を減らしていなくてはならないので難易度が高いといえます。
一方で、業務の一部を単価の低い人に移管し単価引き下げていくやり方は、部分的な業務移管なため簡単にできますが、個人に依存するため効果は限定的。という側面があります。
全体として収益構造に問題あるのであれば前者、部分的な問題なら後者。というように、状況に応じて使い分けていきます。
医師の長時間労働というのであればすべての科に通じることなので、まず、特定の診療科を決めて、そこで業務量を減らすことから始め次に勤務時間を減らす。その効果をみながら他の診療科に広げていく。というがよろしいのではと考えます。
理由はシンプルで、数百人もの人が働く総合病院であれば、業務量の1割を減らすことはそれほど難しいことではないからです。
仮に、人件費比率55%の病院で、最大2割の人件費を下げることが出来たとしたら・・・経常利益はプラスオンさせることも決して夢ではないということです。
具体的には、医師と看護師、技師、医療事務の業務内容がどうなっているのか?すべて棚卸を行い総業務量がどれぐらいあるのか?といったことを把握することから始めていきます。
それをもとに、重複や、形骸化したもの、手間のかかっていること、いわゆる非効率な業務を洗い出します。それを一表にして、今度はどのくらい人件費を削減できるかを算出します。
もちろん、医療業務の中には、勝手に止めたりすることが出来ない業務もあるので、そこは丁寧に確認をしてプロジェクトの中で進めていく訳です。
このように、業務を棚卸しをしていくことで、医師や看護師でなくても出来る医療補助業務として必要な時間がどのくらいなのかは、おのずと見えてきます。
こういいますと、「医師の診療時間は測りにくい」「個々の患者の病状によって変わる」といった声が聞こえてきそうですが
医師の方にご協力いただき、その医師の方のやり方でいいのでそれを実測させてもらってください。と申し上げています。
このデータをもとに、経営から医師に対し、患者一人当たりどれくらいでやってほしいという要請をすることが出来るからです。
こういったことを決めていかない限り、各医師のペースで診察がおこなわれます。
断っておきますが、医師のペースが悪いということではありません。
人は、忙しいときは急いで仕事をやってくれますが、時間に余裕があるときはどうでしょうか?そう、マイペースでゆっくりというのは人の性だからです。
そういったことも含め、医師が一人の患者にかかる実質診察時間を決めてくことが重要になってくるからです。
なぜなら、医師が一人の患者を診療している間、そのうしろで医師から指示が出るを待ってる大勢の看護師、医療補助スタッフにも給与が支払われているということを忘れてはならないということです。
つまり、診療科ごとの業務量の多さや煩雑さが、病院全体の人時生産性の高いか低いかといったことに表れるということです。
こういった、観点から、病院経営における業務の棚卸はとても重要になってくるということです。
さあ、あなたの病院では、まだ、医療は別と言って、業務棚卸の先伸ばししますか?それとも、全ての業務棚卸をやって、抜本的な利益改善を短期間で実現させますか?
著:伊藤稔
