今週の儲かる繁盛店の視点 第604話:「急性期病院の業務改革で最初に経営がやっておくべきこととは?」
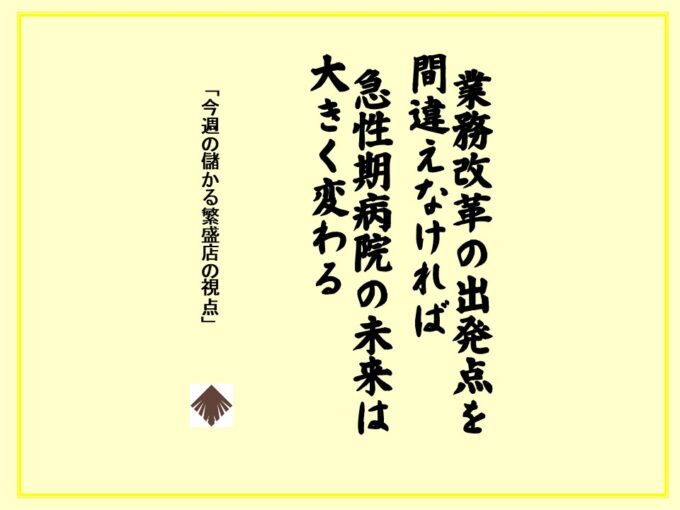
先生、かつてうちの病院でも業務改革を試みたことがあったんです。
とある病院経営者からのご相談です。
お話をお聞きすると・・・
数年前、自動会計機器導入と同時に、全体の業務改革に取り組もうとしたものの、そこだけに終わってしまい、患者の待ち時間や職員の残業改善に至らなかった。
再び、機器の更新時期が近づいているので、そのチャンスを生かすために弊社セミナーに参加されたとのこと。
業革プロジェクトで、こういった残念な結果になってしまうのには、いくつか要因があります。
なかでも多いのが、出発点でやるべきことが明確になっていたか?という問題です。
もし、そこが「曖昧」なままですと、そういったことが起きる可能性が高くなります。
何でもそうですが、結果を得るためには、出発点とゴールがあってどのように進めるのか提示されていることが前提となります。
先のケースの場合、機器の購買が先に決まっていて、その他のことはプロジェクト内で決めていくめていく。といった流れになってました。
ところがいつのまにか、機器導入が目的にすり替わってしまい、結果、業務改善は何も進まなかったということです。
全体目標として患者を待たせない、職員の業務負担を軽減するということだとすれば、出発点で、そのような全体計画が提示されることが必要になります。
なぜなら、走りながら考えてできるほど業務改革は甘くはないからです。
極端な話、その時点で全体計画がなければ、機器更新を中止、延期をするぐらいの覚悟がなければ、業務改革は進めることなどできない。とはっきり申し上げています。
病院経営の未来を考え、本気で、患者の待ち時間解消や従業員の働き方改革を実現するのであれば、最低ここまでは準備して出発点に臨みませんと、同じ轍を踏むということです。
こう申し上げますと
「でも、そんなに人がいるわけではないし・・・」という声が聞こえてきます。
外科でも、外来の診療時と手術時では、人員体制が全く変わってくるように、通常時と業務改革時は体制が全く変わってきます。
通常時は「維持継続」が優先されますが、業務改革時は「未来を作る」ことに重きを置きます。
「未来を作る」とは、現状の問題の特定し、患者の待ち時間改善や職場の環境を良い方向に改善を進めていく姿を描き出すことです
このプロジェクトの活動を通じ、医療の質を向上させ、職員の働き方も変える。結果、利益が2倍3倍と上がっていく未来像は、自らの手で作りあげていかなければならないものだからです。
もし、過去の改装時に、理事長中心に、こうして専属メンバーを設定し、プロのアドバイスを受けながら実施していたらどうなったでしょうか?
資源配分や意思決定をトップが担うことで「これから病院全体の改革が始まる」というメッセージが全館に伝わり、さまざまな変化も始まったことでしょう。
患者動線をもとに職員の業務を可視化し、部門横断で非効率業務を次々改善することもできたはずです。
業務改革は、出発点でやるべきことがどこまで準備できるかどうかで、急性期病院の未来は大きく変わる。ということです。
だからこそ、弊社は出発点づくりのサポートを最重要視しています。
著:伊藤稔
